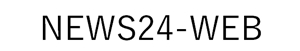「そうりゅう型」潜水艦の最大潜航深度は?

まず、一般的な潜水艦の潜航深度はいくらか?
中国海軍など多くの国が採用しているロシア製「キロ級潜水艦」の安全潜航深度は水深240m、最大潜航深度は水深300mとされる。
海上自衛隊の潜水艦の「安全潜航深度」や「最大潜航深度」は公表されていないが、海上自衛隊の潜水艦救難艦「ちはや」の水中作業員の飽和潜水深度は450mと公表されている。
さらに海上自衛隊は深海救難艇(DSRV)や無人潜水艇(ROV)を保有しているが、これらの耐圧深度は1,000m以上とされる。
また海上自衛隊が保有する潜水艦発射89式魚雷の最大深度は900mとされる。
さらに、そうりゅう型潜水艦には溶接可能な鋼材としては世界最高水準である「NS110鋼材」(耐力110㎏f/mm)が船体の一部に使用されており、計算上、水深1,000mの水圧にも耐えられる。
ちなみに、中国系のサイトでは、そうりゅう型潜水艦の最大潜航深度604m、通常潜航深度(安全潜航深度)500mとしている。
安全係数
例えば、最大潜航深度600mでも安全係数が1.5倍ならば、深度900mまでは耐えられることになる。
日本の「しんかい6500」の最大潜航深度は6,500mだが、安全係数は1.5倍で9,750m、さらに300mを足して、10,050mまで潜れる。
自衛隊の潜水艦の安全係数は不明だが、アメリカの調査用の潜水艇は設計深度の1.25倍、中国は条件次第で1.1倍とされる。
これらから予想すると、自衛隊の潜水艦の安全係数は1.25倍~1.5倍と思われる。
日本の場合、安全に配慮した設計にするので自衛隊の潜水艦の安全係数は1.5倍と予想している。
当ブログでは、そうりゅう型潜水艦の設計上の最大潜航深度は650m、安全係数1.5倍として975mまで潜れると予想している。
| 潜航深度 |
|
| 連続潜航時間
(AIP搭載艦) |
(1ノット=1.852km) |
| 連続潜航時間
(リチウムイオン搭載艦) |
(1ノット=1.852km) |
| 全幅 | 9.1m |
| 全幅 | 9.1m |
| 基準排水量 | 2,900トン(5番艦以降2,950トン) |
| 水中排水量 | 4,200トン |
| 水中速度 |
|
| 水上速度 | 13ノット(時速24km) |
| 乗員 | 65名 |
| 建造費 | 530億円~560億円(11番艦660億円) |
| 兵装 | 533mm魚雷発射管×6門 |
| 水雷等 | 89式魚雷・18式魚雷・ハープーン(合計20発~30発) |
| 航続距離 | 6,000km~8,000km |
| 建造数 | 12隻 |
通常型潜水艦として、自衛隊の「そうりゅう型潜水艦」の性能は世界トップクラスと言える。
2020年3月に就役したリチウムイオン電池搭載の11番艦「おうりゅう」は、同じ速度の場合、「そうりゅう型潜水艦(1番艦~10番艦)」の2倍以上の連続潜航距離となる。
また、当ブログの予想では「待ち伏せ任務」の場合の連続潜航時間は「従来の2週間から1ヵ月間」へと2倍になったと思われる。
ちなみに、キロ級の連続潜航時間は72時間(3日)とされる。
しかし、「リチウムイオン電池の瞬間電流出力は、鉛蓄電池よりも低い」ため、水中最高速度が20ノット(37km/h)から18ノット(33km/h)へと遅くなった予想される。
そもそも、鉛蓄電池搭載の「そうりゅう型潜水艦」の水中最高速度が20ノット(37km/h)と言っても実際に20ノット(37km/h)の速度を出せるのは瞬間的(5分間)だけで、実際の水中最高速度は16ノット(30km/h)でしかない。
一方、リチウムイオン電池を搭載した「おうりゅう」は、連続潜航時でも常時18ノット(33km/h)を出せるので実用的な速度は向上している。
ネット情報では、そうりゅう型潜水艦の最大潜航深度1,000m説がある。
恐らく、そうりゅう型潜水艦の深度計が1,000m以上になっているという目撃情報が根拠になっていると思われる。
しかし、潜水艦の最大深度が650mだとしても、安全係数1.5倍ならば、耐圧深度975mまで耐えられるので、深度計は1,000mまで計測できるようになっていると予想される。
深度計の最大目盛は最大潜航深度ではないが、それが、最大潜航深度と勘違いされた可能性がある。
補足
一般的には、水上や空中からは水深300mまでしか探知できないし、キロ級の最大潜航深度は水深300mなので、潜水艦の最大潜航深度は水深650mで十分と言える。
したがって、最大潜航深度900mと最大潜航深度650mと軍事的な意味では有意差はなく、むしろ、船体の重量増加や建造費の上昇などデメリットが多くなる。
そもそも、台湾海峡や東シナ海の水深は150m~200mなので、もし、900mまで潜れたとしてもその性能を発揮できない。
したがって、そうりゅう型は、潜航深度よりも、台湾海峡や東シナ海などの浅海域での静寂性などを重視した設計になっていると思われる。
一般的に潜水艦は総蓄電容量の1/3~1/4ずつスノーケル充電する。
「そうりゅう型」潜水艦(スターリングエンジン搭載の前期型)のスノーケル充電時間は公称100分とされており、逆算するとフル充電するには300分~400分(5時間~6時間40分)かかる。
一方、リチウムイオン電池は鉛電池と違って急速充電ができ、民生用のリチウムイオン電池の場合、鉛電池の8倍~10倍の速度で充電できる。
したがって「おうりゅう」は従来艦の鉛蓄電池の4倍の総蓄電容量のリチウムイオン電池を搭載していると推定されるが、フル充電時間は鉛蓄電池の充電時間の4倍になるわけではない。
民生用リチウムイオン電池と同様に高速充電できるなら、「おうりゅう」のフル充電時間は「2時間~3時間」と予想される。
総蓄電容量の1/3~1/4ずつスノーケル充電するならは、1回の充電時間は30分~60分となる。
つまり、運用上のスノーケル充電時間は100分から30分~60分と大幅に短縮され、敵に発見されにくくなった。
また、防衛省は、新型スノーケル発電システムを開発しており、これが採用されれば、さらに充電時間が短縮される可能性もある。
| 艦種 | 潜航持続時間 | スノーケル充電時間 | フル充電時間 |
| おやしお型 | 100時間(4日) | 100分 | 300分~400分 |
| そうりゅう型(AIP) | 240時間(10日) | 100分 | 300分~400分 |
| そうりゅう型(リチウムイオン) | 560時間(23日) | 30分~60分 | 120分~180分 |
海上自衛隊「歴代潜水艦」の潜航深度(推定)
| 退役潜水艦 | 建造期間 | 就役期間 | 建造数 | 計画数 | 現役隻数 | 最大潜航深度 |
| ゆうしお型 | 1976年~1989年 | 1980年~2008年 | 10隻 | 10隻 | 0隻 | 450m |
| はるしお型 | 1987年~1997年 | 1990年~2017年 | 7隻 | 7隻 | 0隻 | 550m |
| 現役潜水艦 | 建造期間 | 就役期間 | 建造数 | 現役隻数 | 練習艦・試験艦 | 最大潜航深度 |
| おやしお型 | 1994年~2008年 | 1998年~就役中 | 11隻 | 7隻 | 2隻(練習艦) | 600m |
| そうりゅう型 | 2005年~2021年 | 2009年~就役中 | 12隻 | 12隻 | 0隻 | 650m |
| たいげい型 | 2018年~ | 2022年~就役中 | 12隻 | 3隻 | 1隻(試験艦) | 650m |
| 合計 | 現役22隻 | 3隻 |
2022年3月9日、たいげい型1番艦就役し、現役艦22隻+練習艦2隻の合計24隻となった。
その後、たいげい型1番艦は試験艦となり、現役艦22隻+練習艦2隻+試験艦1隻の合計25隻体制となった。
キロ級潜水艦など世界の多くの潜水艦は水深300mしか潜れないし、対潜水艦ミサイル(アスロック)も水深300~400mしか届かない。
また、他国の潜水艦の魚雷は水深500mより深いところでは、水圧で圧潰するので最大潜航深度650mの「そうりゅう型」潜水艦を攻撃できない。
逆に、そうりゅう型潜水艦は水深650mまで潜航でき、そこから水深300mにいる他国の潜水艦を魚雷攻撃できる。
つまり「そうりゅう型」潜水艦は他国の潜水艦や水上艦から攻撃されることなく、一方的に攻撃できるのだ。
海上自衛隊そうりゅう型潜水艦(SS16)は非大気依存推進装置AIPを搭載している。
これはスターリングエンジンで液体酸素と少量のディーゼル燃料でエンジンを稼動、発電し推力を得るシステムだ。
従来型潜水艦の連続潜航期間は数日だったが、AIP搭載により連続潜航期間は2週間と大幅に延長された。
しかし、AIP使用時の水中速度は5ノット(時速9km)と遅く、またAIP装置は巨大(長さ11m)で乗員の居住区画が小さくなる(長さ-2m)という問題点があった。
11番艦 おうりゅう/12番艦 とうりゅう
AIPの弱点を克服するため「そうりゅう型潜水艦11番艦 おうりゅう」と「12番艦 とうりゅう」はスターリングエンジンを廃止し、体積エネルギー密度が鉛蓄電池の4倍のリチウムイオン電池(GSユアサ・テクノロジー社製)を採用した。(リチウムイオン電池の重量は鉛電池の1/2なので重量エネルギー密度は2倍)
ただし、リチウムイオン電池は、体積エネルギー密度を上げると「発火」の危険性が高まる。したがって、体積エネルギー密度は本来4倍だが、潜水艦用のリチウムイオン電池の体積エネルギー密度は3倍くらいに抑えているのではないか?
AIP区画(長さ11m)を廃止し、そこにもリチウムイオン電池を設置していると予想される。
| 艦級 | おやしお | そうりゅう(前期) | おうりゅう(そうりゅう型11番艦) | たいげい型 |
| 電池個数 | 120個×4群=480個 | 120個×4群=480個 | 320個×2群=640個 | 340個×2群=680個 |
| 電池種類 | 鉛 | 鉛 | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 総蓄電容量 | 1とする | 1 | 1.33×3=4倍 | 1.42×3=4.3倍 |
- 2022年10月、民放テレビ番組で、現役の海上自衛官が「せきりゅう(そうりゅう型)の電池は480個」と発言したので、当ブログの推定は正しいと分かった。
当ブログの推定では、そうりゅう型11番艦「おうりゅう」の総蓄電容量は、従来型艦の約4倍、たいげい型は約4.3倍と予想される。
また、リチウムイオン電池は高価なため、建造費は660億円となった。
リチウムイオン電池の採用により従来型艦(AIP使用時時速9km 5ノット)よりも、高速で潜航でき連続潜航日数は2週間から30日(1ヵ月)と長くなった。
そもそも「そうりゅう型潜水艦」は海峡などのチョークポイントで待ち伏せする場合、潜航中はそれほど移動せず、スターリングエンジンで十分だった。
しかし、リチウムイオン電池搭載「そうりゅう型潜水艦11番艦(おうりゅう)」は、連続潜航航続距離が約4倍に伸びたことにより「ゲール・デ・クルース」(巡洋艦戦略)も可能となった。もちろん、待ち伏せ作戦を行うこともあり、その場合1ヵ月間潜航できる。
電池8倍説は疑問
そうりゅう型のAIP区画と廃止し、そこにリチウムイオン電池を以前の鉛蓄電池と同じ容量を搭載するため、電池個数は2倍で体積エネルギー密度4倍とし、総蓄電容量は8倍とするwebメディアもある。
しかし、電池個数を記載しておらず、単純にスペースが2倍になるから電池個数も2倍と仮定しているに過ぎない。
当ブログでは、そうりゅう型の電池個数「120個×4群=480個」から「320個×2=640個」へ1.33倍しか増加していないと推定している。
また体積エネルギー密度4倍というのはスマホなどの小容量の場合で、「おうりゅう」のような大規模な場合、発火の危険性も考慮して体積エネルギー密度を3倍に抑えていると予想される。
連続潜航距離(当ブログの予想)
| 艦種 | 電池種類 | 速度 | 潜航持続時間 | 連続潜航距離 |
| おやしお型 | 鉛蓄電池 | 4ノット(7km/h) | 100時間(4日) | 740km |
| そうりゅう型(前期型) | 鉛蓄電池 | 4ノット(7km/h) | 140時間(6日) | 1,037km |
| AIP(スターリングエンジン) | 5ノット(9km/h) | 100時間(4日) | 926km | |
| 合計 | 4.4ノット(8km/h) | 240時間(10日) | 1,922km | |
| そうりゅう型(おうりゅう) | リチウムイオン電池 | 4ノット(7km/h) | 560時間(23日) | 4,148km |
| 8ノット(15km/h) | 140時間(6日) | 2,074km | ||
| 12ノット(22km/h) | 62時間(2.6日) | 1,378km | ||
| 16ノット(30km/h) | 35時間(1.5日) | 1,037km |
- そうりゅう型から永久磁石同期モーター(PMSM)が採用されエネルギー効率が40%向上し、同じ鉛蓄電池を使用しても連続潜航距離は40%伸びたと予想される。
- 「おうりゅう」はリチウムイオン電池を搭載し、総蓄電量は「そうりゅう型(前期)」の4倍になったと予想される。
そうりゅう型の11番艦「おうりゅう」は世界で初めてリチウムイオン電池を搭載 しています。従来のそうりゅう型に比べ、航続距離や潜航時間が飛躍的に向上しました。同じ速度で潜航した場合、2倍以上の時間潜ることもできるとみられています。
引用 テレビ朝日 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000178172.html
リチウムイオン電池の体積エネルギー密度は鉛蓄電池の3倍~4倍なのに、潜航時間が2倍以上となっているのは少ないと思う。
それは、そうりゅう型潜水艦(AIP搭載)のAIPも使用した場合と比較して「潜航時間が2倍以上」としていると思われる。
同じ速度で潜航した場合というのはAIPを使用した場合なので、速度は「4ノット(7km/h)~5ノット(9km/h)」で比較したと予想される。
- そうりゅう前期型 1,880km「4.4ノット(8km/h)」
- おうりゅう 3,920km「4ノット(7km/h)」
4ノット(7km/h)~5ノット(9km/h)は、かなり遅い速度なので実用的な潜航距離としては使えない。
実戦能力としては、16ノット(30km/h)で35時間、1,050kmというのが目安になる。作戦半径としてはその半分の約500km程度ではないか?
| 艦名 | 進水 | 就役 | 配備基地 | |
| 1番艦 | そうりゅう | 2007年12月 | 2009年3月 | 呉基地 |
| 2番艦 | うんりゅう | 2008年10月 | 2010年3月 | 呉基地 |
| 3番艦 | はくりゅう | 2009年10月 | 2011年3月 | 呉基地 |
| 4番艦 | けんりゅう | 2010年11月 | 2012年3月 | 呉基地 |
| 5番艦 | ずいりゅう | 2011年11月 | 2013年3月 | 横須賀基地 |
| 6番艦 | こくりゅう | 2013年10月 | 2015年3月 | 横須賀基地 |
| 7番艦 | じんりゅう | 2014年10月 | 2016年3月 | 呉基地 |
| 8番艦 | せきりゅう | 2015年11月 | 2017年3月 | 呉基地 |
| 9番艦 | せいりゅう | 2016年10月 | 2018年3月 | 横須賀基地 |
| 10番艦 | しょうりゅう | 2017年11月 | 2019年3月 | 呉基地 |
| 11番艦 | おうりゅう | 2018年10月 | 2020年3月 | 呉基地 |
| 12番艦 | とうりゅう | 2019年11月 | 2021年3月24日 | 横須賀基地 |
2021年3月、12番艦「とうりゅう」が横須賀基地に配備され「そうりゅう型潜水艦」の配備数は呉基地に8隻、横須賀基地に4隻となった。
首都圏の横須賀基地よりも西日本の呉基地の方が配備数が多い。
これは尖閣列島など南西諸島に「そうりゅう型」潜水艦を派遣するには、呉基地の方が距離的に近いからだ。
尖閣列島やパシー海峡(台湾~フィリピンに位置し海峡幅100km・水深1500m以上)周辺に「そうりゅう型潜水艦」を含め常時5隻~8隻の潜水艦を配置しているとの情報もある。
海自潜水艦を16隻から22隻体制へ
従来、海自自衛隊の潜水艦は現役16隻+練習艦2隻の18隻体制だったが、2022年3月9日に現役22隻(+練習艦2隻の24隻)体制になった。今後は次期潜水艦の就役と同時に順次「おやしお型潜水艦」を退役させる。
2022年3月9日現在の就役数
| 型級 | 現役 | 練習艦 | 合計 |
| おやしお型 | 9隻 | 2隻 | 11隻 |
| そうりゅう型 | 12隻 | 12隻 | |
| たいげい型(最新) | 1隻 | 1隻 | |
| 合計 | 22隻 | 2隻 | 24隻 |
原子力潜水艦との性能比較
原子力潜水艦の最大潜航深度は500~700mと推測される。中には深度900m~1,000mと言われることがあるが、米ソ冷戦時代に建造された超高性能・超高価な数隻の原潜(米・シーウルフ級など)のみだ。
現在の米国海軍の主流である「ロサンゼルス級原潜」は水中排水量約7,000トンと大型のため、潜航深度は600m程度とされる。
原潜は原子炉を停止することができないので、運転音が通常型潜水艦よりも大きい。さらに原子炉からの熱は最終的に海中に放出されるので、原潜の周囲の海水温が高くなり探知されやすくなる。
したがって、静粛性は「たいげい型」が優位、潜航深度も「たいげい型」は原潜と同等以上と思われる。
潜航期間、航続距離は原潜の方が圧倒的に有利だが、日本周辺海域であれば、1か月の潜航期間の「たいげい型」でも不利とはならない。
コメント
プロペラスクリューを廃止し原子力潜水艦と同じ「ウォータージェット推進」であれば、さらに静粛性と高速性が高まる。
ウォータージェット推進はプロペラ推進よりもエネルギー効率(燃費)が悪いが、静粛性と高速性が高い。
例えば、全固体リチウムイオン電池が採用され蓄電量が多くなれば「ウォータージェット推進」が採用される可能性はある。
「たいげい」型潜水艦は、水深200m以下の東シナ海のように浅い海域でも発見されにくくなる。
「たいげい」「そうりゅう型」潜水艦が40隻あれば、日本は中国海軍を完全に海上封鎖できる。
建造費は700億円と予想されるので40隻で2兆8000億円となるが、中国は完全に日本に対して手も足も出せなくなる。
また、そうりゅう型潜水艦は1隻あたり20発~30発の魚雷を搭載していると予想されるので、尖閣列島に5隻配備すれば中国軍艦100隻を1時間以内に全滅させることができる。
なぜ1時間かかるかというと、海自の89魚雷の最高速度は120km/hなので、12km先の中国軍艦を撃沈するのに6分、36km先だと撃沈するまで18分かかる。
海自の89魚雷は途中まで有線で誘導するので、魚雷20発を6門の発射口から発射するのに30分~1時間かかるからだ。
某youtuberは潜水艦の待ち伏せ攻撃を「単なる機雷」と言って否定しているが、それは大きな間違い。
戦後、長らく日本の潜水艦は16隻しかなかった。たった16隻で日本列島全体を防衛することは不可能なので、海峡(チョークポイント)で待ち伏せ攻撃するしかない。
さらに水上艦艇、例えばイージス艦「あたご」の速力は30ノット(時速55km)だが、そうりゅう型潜水艦の水中最高速度は20ノット(時速37km)でしかない。
通常型潜水艦が水上艦艇に追いつくことは不可能で、通常型潜水艦は今でも「待ち伏せ攻撃」が基本と言える。