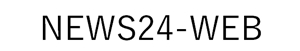出典 海上自衛隊 https://www.mod.go.jp/msdf/
最新鋭潜水艦「たいげい型」仕様(当ブログ推測を含む)
最大潜航深度は国家機密(特定秘密)であり個人が知りえるはずもなく、個人ブログの推測です。
また、断片的な情報をまとめたもので数値に整合性がない場合があります。
潜航深度については、キロ級潜水艦は300m、ドイツ214潜水艦は400m、対潜哨戒機の探知深度は300mであることから、深度500m以上の性能があってもあまり意味はない。
総合的に考えると、たいげい型潜水艦の安全潜航深度(通常運用)は500m、最大潜航深度は650m、設計上の耐圧深度は975mと推定される。
- 深度1000mにも耐える「NS110鋼材」を一部に使用している。
- 2008年、潜水艦救難艦「ちはや」の潜水士は水深450mの飽和潜水を成功した。
- 自衛隊のDSRV(深海救難艇)の最大潜航深度は1,000m以上と言われる。
- たいげい型に搭載される「18式魚雷」の最大深度は900mと言われる。
上記理由から、たいげい型の最大潜航深度を900mとする説がある。しかし、中国の潜水艦の最大潜航深度が300m、東シナ海の水深は200mなので、900mまで潜っても意味がない。逆に、重量増加、建造費増加などのデメリットの方が多いので、最大潜航深度900m説は疑わしい。
もっとも、安全係数を1.5とすると、水深975mでも生存できると思うし、潜水艦の水深メーターの目盛りは1,000mまであると思われる。そこから、最大潜航深度900m説が噂されるようになったと思う。
通常動力潜水艦の連続潜航日数は3日、AIPを搭載した「そうりゅう型潜水艦」は2週間、リチウムイオン電池を搭載した「たいげい型潜水艦」は1か月と推定される。
しかし、これは海峡などの待ち伏せ作戦の場合で、「たいげい型潜水艦」も16ノット(30km/h)で海中を航行すると37時間、潜航距離1,110kmしか電池が持たない。
| 項目 | たいげい型 |
| 安全潜航深度 | 500m |
| 最大潜航深度 | 650m |
| (設計上の耐圧深度) | 975m:650m×安全係数1.5 |
| 全長 | 84m |
| 全幅 | 9.1m |
| 高さ(深さ) | 10.4m |
| 軸出力 |
|
| 基準排水量 | 3,000トン |
| 水中排水量 | 4,300トン |
| 水中速度 | 20ノット(時速37km) |
| 水上速度 | 13ノット(時速24km) |
| 航続距離 | 8,000km(予想) |
| 連続潜航時間 | 約1ヶ月(予想) |
| 通常の航海日数 | 約3ヶ月(予想) |
| 乗員 | 約70名 |
| 建造費 |
|
| 機関 |
|
| 建造数 | 9隻(予想) |
川崎12V 25/31型ディーゼル機関
海上自衛隊の最新鋭潜水艦「たいげい型4番艦らいげい」が2025年3月6日に就役した。
1番艦~3番艦の機関は「川崎12V 25/25SB型ディーゼル機関2基」だったが、4番艦から大型の「川崎12V 25/31型ディーゼル機関2基」を初搭載した。
新型機関「川崎12V 25/31型ディーゼル機関2基」は、発電出力が大きくなりスノーケル充電が短縮された。
| 機関 | 仕様(予想) |
|---|---|
| 川崎12V 25/25SB型 | V型12気筒4ストローク
(ストローク250mm×ボア250mm) 排気ターボ過給と機械駆動過給の2段過給方式 |
| 川崎12V 25/31型 | V型12気筒4ストローク
(ストローク310mm×ボア250mm) 排気ターボ過給と機械駆動過給の2段過給方式 |
(当ブログの推定)
リチウムイオン電池は大容量で充電できるので発電量を多くする必要がある。
一般的に、エンジンの回転数を上げると発電量は多くなるが、トルクが低下しエンジン出力は低下する場合がある。
- エンジンの回転数を上げる → 発電量が増加(充電に有利)
- エンジンの回転数を上げる → トルクが低下しエンジン出力は低下?(水上航行に不利)
そうりゅう型の8,000馬力から、たいげい型の6,000馬力と出力が低下したのは、発電量を増加させるため、エンジンの回転数を上げ出力が低下したと推定される?
そこで、新型「川崎12V 25/31型」は「ストローク310mm×ボア250mm」とロングストローク化により大排気量化し出力を上げたと予想される。
ただし、軸出力は6000馬力と1番艦~3番艦と同じ。
第11潜水隊を新編
潜水艦隊隷下に第11潜水隊を新編した。これは「たいげい型1番艦たいげい」が試験潜水艦に種別変更されたことに伴う組織改編の一環と思われる。
たいげい型潜水艦の全長は84.0m、全幅9.1m、深さ10.4m。
そうりゅう型潜水艦(2,900トン / 5番艦以降2,950トン)よりも基準排水量が50トン~100トン増加し、3,000トンとなった。
また、そうりゅう型潜水艦11番艦「おうりゅう」・12番艦「とうりゅう」と同じくAIP(スターリングエンジン)を廃止し、GSユアサ製の大容量リチウムイオン電池を搭載している。
そうりゅう型潜水艦は、貫通式潜望鏡1本と非貫通式潜望鏡1本だったが、たいげい型は非貫通式潜望鏡2本となった。
非貫通型潜望鏡は高性能のデジタル画像で全周を瞬時に撮影できるので、潜望鏡を海上に突き出す時間が短くなり敵に発見されにくくなった。
たいげい型は、対中国戦を念頭に水深約200mの「東シナ海」での作戦に最適化するため、潜航深度の改善よりも、浅海域での隠密性を主として改善したと思われる。
三菱重工製と川崎重工製の違い
- 三菱重工製:艦橋の扉の形状が四角
- 川崎重工製:艦橋の扉の形状が丸角
現役艦22隻体制
たいげい型1番艦SS-513「たいげい」(大鯨)は2020年10月14日、神戸市の三菱重工業神戸造船所で進水、2022年3月9日に就役し、神奈川県の横須賀基地に配備された。
これにより、現役艦22隻体制(練習艦2隻を含め24隻体制)が完成した。
今後は、1隻就役すると、1隻が退役することで現役艦22隻体制(練習艦2隻・試験艦1隻を含め25隻体制)を維持する。
「たいげい型」と「そうりゅう型」の性能比較(当ブログ推測)
また、潜航深度と言ってもいろんな意味がある。
ここでは、通常運用深度を「最大潜航深度」とし、それに安全係数1.5(旧・日本海軍基準)を掛けた深度を「設計上の耐圧深度」とする。
もちろん、安全係数も国家秘密(特定秘密)なので、当ブログの推測です。
当ブログの推測では、潜水艦の深度計は「設計上の耐圧深度の1,000m」まで表示されいて、それを見た人が「1,000mまで潜れる」と噂したのだと思う。
| 項目 | たいげい型 | そうりゅう型 |
| 潜航深度 |
|
|
| 全長 | 84m | 84m |
| 全幅 | 9.1m | 9.1m |
| 高さ(深さ) | 10.4m | 10.3m |
| 主機関 | ディーゼル電気推進(1軸)
|
|
| 軸出力 | 6,000馬力 |
|
| 基準排水量 | 3,000トン | 2,900トン(5番艦以降2,950トン) |
| 水中排水量 | 4,300トン | 4,200トン |
| 水中速度 | 20ノット(時速37km) | 20ノット(時速37km) |
| 水上速度 | 13ノット(時速24km) | 13ノット(時速24km) |
| 乗員 | 約70名 | 65名 |
| 建造費 |
|
|
| 兵装 | HU-606 533mm魚雷発射管×6門 | HU-606 533mm魚雷発射管×6門 |
| 水雷等 | 18式魚雷・89式魚雷・ハープーン・ブロック2(推定合計18発~30発) | 18式魚雷・89式魚雷・ハープーン(推定合計18発~30発) |
| 航続距離 | 8,000km(予想) | 8,000km(予想) |
| 連続潜航時間 | 約1ヶ月(予想) | 約2週間(予想) |
| 建造数 | 9隻(予想) | 12隻 |
- たいげい型は「UGM-84Lハープーン・ブロック2(射程248km)」を搭載可能で、魚雷発射管から発射できる。敵基地に距離約200kmまで接近すれば、海中から敵基地を攻撃できる。
- 魚雷搭載本数は、魚雷発射管1門につき3本とすると18本、魚雷発射管1門につき4本とすると24本となるので、18本または24本が有力。しかし、最大30本の可能性もある。
参照 人民網日本版では30発としている
海上自衛隊「歴代潜水艦」の潜航深度(推定)
| 退役潜水艦 | 建造期間 | 就役期間 | 建造数 | 計画数 | 現役隻数 | 最大潜航深度 |
| ゆうしお型 | 1976年~1989年 | 1980年~2008年 | 10隻 | 10隻 | 0隻 | 450m |
| はるしお型 | 1987年~1997年 | 1990年~2017年 | 7隻 | 7隻 | 0隻 | 550m |
| 現役潜水艦 | 建造期間 | 就役期間 | 建造数 | 現役隻数 | 練習艦(試験) | 最大潜航深度 |
| おやしお型 | 1994年~2008年 | 1998年~就役中 | 11隻 | 7隻 | 2隻(練習) | 600m |
| そうりゅう型 | 2005年~2021年 | 2009年~就役中 | 12隻 | 12隻 | 0隻 | 650m |
| たいげい型 | 2018年~ | 2022年~就役中 | 9隻(予定) | 3隻 | 1隻(試験) | 650m |
| 合計 | 現役22隻 | 練習艦2隻
試験艦1隻 |
2022年3月9日、たいげい型1番艦就役し、現役艦22隻+練習艦2隻の合計24隻体制となった。
2024年7月16日の産経新聞では「海自は計25隻の潜水艦を保有」と記載している。
もしかしたら、たいげい型1番艦が試験潜水艦に種別変更されたため、現役艦22隻+練習艦2隻+試験潜水艦1隻=25隻体制になったのかもしれない。
AIP(非大気依存推進装置 スターリングエンジン)廃止
最新鋭「たいげい型」潜水艦はAIP(非大気依存推進装置 スターリングエンジン)を廃止し、リチウムイオン電池を搭載する。
このリチウムイオン搭載により連続潜航距離が飛躍的に伸び、従来の「待ち伏せ作戦」から原子力潜水艦のような「遠洋航行作戦(巡洋艦作戦)」が可能となった。
そこには、防衛省が本気になって尖閣列島を中国軍から防衛し、さらに南シナ海にも展開する意図が感じられる。中国海軍にとっては極めて強力な脅威となる。
最新鋭「だいげい型」潜水艦の開発目標
「そうりゅう型」の1番艦~10番艦はAIP(非大気依存推進装置・スターリングエンジン)を搭載している。
しかし、このAIP(スターリングエンジン)では水中速度が時速9kmと遅く、また設置面積(容積)が大きいため、居住スペースを圧迫していた。AIP区画の長さは11mで、おやしお型に比べて居住区間は-2m減少したと推定される。
そこで新型潜水艦「たいげい型」は大容量リチウムイオン電池を搭載し、水中速度の向上と居住スペースを確保することにした。
将来的には、全固体電池や燃料電池を搭載する可能性もある思う。
連続潜航航続距離(当ブログ予想)
連続潜航距離などは国家機密であり個人が知りえるはずもなく、単なる個人の予想です。
一般的には、リチウムイオン電池は鉛電池の4倍の体積エネルギー密度だが、実際に潜水艦に搭載する場合は隔壁を厚くするため、体積エネルギー密度は3倍と予想される。
| 艦種 | おやしお | そうりゅう(前期)電池のみ | おうりゅう/とうりゅう | たいげい |
| 電池個数 | 240個×2=480基 | 240個×2=480基 | 320個×2=640基 | 340個×2=680基 |
| 電池種類 | 鉛 | 鉛 | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 総蓄電容量 | 1倍 | 1倍 | 1.33×4=4倍 | 1.42×4=4.3倍 |
つまり、総蓄電容量は、「おやしお型」を1倍とすると、「おうりゅう(そうりゅう型)」は約4倍、たいげい型は約4.3倍と予想される。
| 艦種 | 電池種類 | 速度 | 連続潜航時間 | 連続潜航距離 |
| おやしお型 | 鉛蓄電池 | 4ノット(7km/h) | 100時間(4日) | 700km |
| そうりゅう型(前期型) | 鉛蓄電池 | 4ノット(7km/h) | 140時間(6日) | 980km |
| AIP(スターリングエンジン) | 5ノット(9km/h) | 100時間(4日) | 900km | |
| 合計 | 4.4ノット(8km/h) | 240時間(10日) | 1,880km | |
| そうりゅう型(おうりゅう) | リチウムイオン電池 | 4ノット(7km/h) | 560時間(23日) | 3,920km |
| 8ノット(15km/h) | 140時間(6日) | 2,100km | ||
| 12ノット(22km/h) | 62時間 | 1,364km | ||
| 16ノット(30km/h) | 35時間 | 1,050km | ||
| たいげい型 | リチウムイオン電池 | 4ノット(7km/h) | 600時間(24日) | 4,200km |
| 8ノット(15km/h) | 150時間(6日) | 2,250km | ||
| 12ノット(22km/h) | 66時間 | 1,452km | ||
| 16ノット(30km/h) | 37時間 | 1,110km |
そうりゅう型から永久磁石同期モーター(PMSM)が採用されエネルギー効率が40%向上したと予想される
「おうりゅう」はリチウムイオン電池(640セル)を搭載し、総蓄電容量は「そうりゅう型(前期)」の4倍になったと予想される
たいげい型は、リチウムイオン電池(680セル)を搭載し、総蓄電容量は「おうりゅう」よりも約6%増加していると予想される
沖縄県~南シナ海の距離は約1,800kmなので、往復するには約4,000kmの連続潜航距離が必要とされる。
そうりゅう型(AIP搭載)は時速9km以下で潜航したまま1,880km航行できる(予想)
最新鋭潜水艦「たいげい型」は時速15kmなら潜航したまま2,250km航行でき、時速7kmならば4,200km航行できる(予想)
当ブログの試算では、沖縄本島沖から南シナ海へは「そうりゅう型(AIP搭載)」なら潜航したままで9日かかるが、「たいげい型」なら5日で行けることになる。
また、「たいげい型潜水艦」はスノーケル充電しながら航行すれば最速2日~3日で到達できる。
スノーケル充電時間の短縮
一般的に潜水艦は総蓄電容量の1/3~1/4ずつをスノーケル充電する。
「そうりゅう型」潜水艦(スターリングエンジン搭載の前期型)のスノーケル充電時間は公称100分とされており、逆算するとフル充電するには300分~400分(5時間~6時間40分)かかる。
一方、リチウムイオン電池は鉛電池と違って急速充電ができ、民生用のリチウムイオン電池の場合、鉛電池の8倍~10倍の速度で充電できる。
「おうりゅう」は従来艦の鉛蓄電池の4倍の総蓄電容量のリチウムイオン電池を搭載していると推定されが、フル充電時間は鉛蓄電池の充電時間の4倍となるわけではない。
民生用リチウムイオン電池と同様に高速充電できるなら、「おうりゅう」のフル充電時間は「2時間~3時間」と予想される。
総蓄電容量の1/3~1/4ずつスノーケル充電するならは、充電時間は30分~60分となる。
つまり、運用上のスノーケル充電時間は100分から30分~60分と大幅に短縮され、被探知性能が向上した。(敵に発見されにくくなった)
防衛省は、新型スノーケル発電システムを開発しており、「たいげい型潜水艦」の4番艦「らいげい」に搭載された。こてにより、さらに充電時間が短縮されるた。
新型スノーケル発電システム
- 充電時間の短縮により、作戦海域での滞在時間極大化を図る
- 小型・高出力化及び静粛化
- 艦の被探知防止性の確保
| 艦種 | 潜航持続時間 | スノーケル充電時間 | フル充電時間 |
| おやしお型 | 1週間~10日 | 100分 | 300分~400分 |
| そうりゅう型(AIP) | 2週間~3週間 | 100分 | 300分~400分 |
| そうりゅう型(リチウムイオン) | 1ヶ月以上 | 30分~60分 | 120分~180分 |
| たいげい型(初期) | 1ヶ月以上 | 30分~60分 | 120分~180分 |
| たいげい型(4番艦以降) | 1ヶ月以上 | 20分~40分 | 100分~160分 |
潜航持続時間とは、海底近くで待ち伏せ作戦をする場合の時間で、2~3ノットの速度で試算
全固体リチウムイオン電池
そもそも、潜水艦に搭載する「リチウムイオン電池」は交換可能なので、将来的には「全固体リチウムイオン電池」に交換するだけで、連続潜航距離を飛躍的に伸ばすことができる。
- リチウムイオン電池は鉛電池の4倍の体積エネルギー密度(現時点では3倍)
- 全固体電池はリチウムイオン電池の3倍の体積エネルギー密度
実際には、鉛電池を1とするとリチウムイオン電池は3倍、全固体電池は9倍くらいではないか?
したがって、全固体電池搭載により、連続潜航距離は時速22km(12ノット)で4,400kmになると予想される。
さらに、待ち伏せ攻撃の場合の連続潜航日数は3ヶ月と予想される。
尖閣周辺海域での「そうりゅう型」潜水艦の弱点
尖閣列島は東シナ海の大陸棚の末端に位置しており、尖閣列島の北側には水深100m~200mの浅い海が中国大陸まで続く。
一般的に潜水艦は水深300mより浅いと敵の哨戒機に発見される可能性が極めて高い。したがって、そうりゅう型潜水艦と言えども、水深300m以下の尖閣列島の北側には容易には展開できない。
一方、尖閣から南側は12km沖で水深500m、15km沖で水深1,000mと急激に深くなっている。
したがって、そうりゅう型潜水艦は水深の深い尖閣列島の南側から、尖閣列島の北側に展開する中国艦船を攻撃することになる。
しかし、「そうりゅう型」に搭載する「89式魚雷」は、尖閣列島の北側のような浅い海では、岩礁など障害物を目標と誤認する可能性がある。
そのために、浅い海でも正確に自律誘導できる新型魚雷「18式魚雷(開発名称G-RX6魚雷)」が必要となった。
最新鋭「たいげい型」潜水艦の尖閣対応装備
最新鋭「たいげい型」潜水艦は、尖閣列島で中国軍との戦闘を念頭に、水深200m以下の東シナ海に対応する。
1 新型魚雷「18式魚雷(G-RX6魚雷)」
まず、浅い海でも中国艦船を撃沈できる新型魚雷を開発した。それが「18式魚雷(G-RX6魚雷)」で現行の「89式魚雷」の次世代モデルとなる。有線誘導と自立誘導で命中率を向上させる。
敵の囮(おとり・デコイ)装置を回避し敵艦に命中できる。また、地形が複雑な浅海域から深海域まで対応する万能魚雷となる。
平成30年度に実戦配備される予定で、新型潜水艦の就役予定平成33年度には十分に間に合う。
2 次世代音響(ソナー)システム
艦首型アレイ(BOW ARRAY)、えい航型アレイ(TOWED ARRAY)、側面型アレイ(SIDE ARRAY)の各ソナーからの信号を処理し敵艦艇の運動解析を自動的に行い、戦闘指揮のレコメンドを行う高度なシステムを採用する。(SIGNAL PROCESSOR)
3 低騒音性の向上
流体雑音低減型潜水艦船型の研究試作を行っており、大型化する新型潜水艦でも静穏性を維持できる。また浮甲板構造(フローティングデッキ)を採用した。
4 新型「たいげい型」の魚雷搭載本数は?
現行の「そうりゅう型」潜水艦には20本~30本の魚雷やハープーンが搭載されていると予想される。通常であれば十分な魚雷本数だ。
しかし、尖閣列島海域で中国艦艇50隻~100隻が尖閣に飽和攻撃を仕掛けてきた場合、魚雷を打ち尽くせば、一旦、佐世保や呉の母港、あるは潜水艦母艦まで戻らないといけない。
新型潜水艦「たいげい型」は船体を大型化(50トン~100トン)しており、「そうりゅう型」より多くの魚雷を搭載できる可能性がある。
5 VLSは搭載されるか?
尖閣での中国軍との対決の場合、日本の潜水艦は水深1,000mの深い南側に展開、中国軍は北側の水深100m~200mの海域に展開する。
海自が魚雷攻撃する場合、中国軍艦は尖閣列島の影に隠れて攻撃しにくい。
新型潜水艦「たいげい型」にVLS(垂直発射装置)を搭載して、長距離ミサイルを搭載することは技術的には可能である。
しかし、「そうりゅう型」潜水艦でも、魚雷発射管から対艦ミサイル「ハープーン」(射程約248km)を発射できるのでそれで対応するだろう。一般的にVLSを搭載すれば、耐圧性能が低下し、潜航深度が浅くなるので今回は見送りされたと考えられる。
6 リチウムイオン電池
リチウムイオン電池は、潜水艦用主蓄電池(SLH)と呼ばれジーエス・ユアサ テクノロジー製(GYT)が2017年3月から量産を始め、2018年8月に納入すると公表された。
リチウムイオン電池は鉛電池の4倍の電気容量を持つため、同じ容積なら4倍の航続距離となる。(ただし、実際に搭載されているリチウムイオン電池は鉛電池の3倍程度ではないか?)
さらに、従来のAIP(スターリングエンジン)を廃止しそのスペースにリチウムイオン電池を搭載するため、蓄電容量は従来型の4.3倍となると予想される。
7 永久磁石同期モーター
そうりゅう型から搭載された永久磁石同期モーター(PMSM)が引き続き採用される。
従来型モーターの回転子は「コイル(銅線)を巻いていたため、大出力にすると発熱量が大きくなる」という欠点があった。
しかし、コイル(銅線)を永久磁石に置き換えると電気を流す必要がなくなり、発熱量も少なくなり、消費電力も低下するというメリットがある。
また、発熱量が少なくなったことで密閉型モーターとなり、騒音やメンテナンスの点で有利となる。
この永久磁石を回転子に使ったモーターは「永久磁石同期モーター(Permanent Magnet Synchronous Motor:PMSM)」と呼ばれ、世界で初めて東芝が開発した。
ネオジム(レアメタル)、鉄、ホウ素化物で強力な永久磁石を作ることができる。
2006年頃から鉄道車両用モーターに採用されており、エネルギー変換効率が90%以上と従来型の誘導電動機よりも約40%も向上した。
この永久磁石同期モーターは密閉型なので潜水艦の騒音レベルを約10dB程度低減できると予想される。
8 ウォータージェット推進型
スクリューに代わって、ウォータージェット推進型と予想されていたが、従来通りのスクリュー推進となったようだ。
エネルギー効率は、スクリュー型の方が高いため、ウォータージェット推進型は採用されなかったのかもしれない。
しかし、将来的にはウォータージェット推進型を採用する可能性はあると思う。エネルギー効率以外では、ウォータージェット推進型の方が性能が高く、原子力潜水艦と同じ推進形式で高速連続潜航に適しているからだ。
全固体リチウムイオン電池を採用し、蓄電量が増加すると、ウォータージェット推進型を採用するかもしれない。
ただし、原子力潜水艦は時速37kmのまま数年間でも潜水したま航行できるが、通常型潜水艦は全固体リチウムイオン電池を搭載したとしても1日~2日間しか連続潜航できないという大きな違いがある。
しかし、1日~2日間は原子力潜水艦のように運用できるので、潜水艦を多数保有し、交代しながら運用すれば、原子力潜水艦に匹敵する威力を持つことが出来る。
もっとも、作戦半径は1,000km~2,000km以内で作戦海域は日本近海に限られる。
9 ケーブルセンサー網
潜水艦は水中にいる場合、外部と通信ができない。しかし海上自衛隊は日本近海にケーブルセンサー網を張り巡らせ、水中の潜水艦と通信していると言われる。
実際、沖縄県うるま市海上自衛隊沖縄海洋観測所から2本の海底ケーブルが敷設されており、1本は尖閣諸島方面、1本は本土方面に伸びている。
これを利用すれば、E-767、P-3C、P-1、E-2Cが敵艦艇の位置を捕捉し、水中の潜水艦とデータリンクすることで、そうりゅう型潜水艦から、対艦ミサイル「ハープーン」を発射できる。
この場合、そうりゅう型潜水艦は、アクティブソナーなどを発することなく、敵艦艇の位置を把握し、魚雷やハープーンを発射できる。
中国艦艇が日本近海に接近すると自衛隊が中国艦船の位置を把握し、ケーブルセンサー網を通じて、24時間体制で警戒監視をしている「そうりゅう型」潜水艦と交信し、いつでも中国艦艇を撃沈できる状態になる。
しかし、潜水艦の魚雷搭載本数は1隻当たり20発と予想されるので、2隻で40発、3隻で60発しかない。
中国艦艇が100隻以上で飽和攻撃を仕掛けてきた場合、現状の潜水艦数では魚雷が不足する。
海自潜水艦22隻体制になれば、尖閣諸島には潜水艦部隊2個隊(潜水艦4隻~6隻)が割り当てられると予想される。
しかし、潜水艦を運用するには年間数か月の補修期間が必要なので、実際に常時配備できるのは3隻~4隻にとどまる。
やはり日本列島を防衛するには潜水艦40隻は必要と思われる。
たいげい型潜水艦の配備数と配備基地
| 番艦 | 艦名 | 起工 | 進水 | 就役 | 配備基地 |
| 1番艦 | たいげい(大鯨) | 2018年3月 | 2020年10月 | 2022年3月 | 横須賀(試験潜水艦) |
| 2番艦 | はくげい(白鯨) | 2019年1月 | 2021年10月 | 2023年3月 | 広島・呉 |
| 3番艦 | じんげい(迅鯨) | 2020年4月 | 2022年10月 | 2024年3月 | 横須賀 |
| 4番艦 | らいげい(雷鯨) | 2021年3月 | 2023年10月 | 2025年3月 | 広島・呉 |
| 5番艦 | ちょうげい(長鯨) | 2022年4月 | 2024年10月 | 2026年3月 | |
| 6番艦 | 2023年3月 | 2025年10月 | 2027年3月 | ||
| 7番艦 | 2024年4月 | 2026年10月 | 2028年3月 | ||
| 8番艦 | 2025年3月 | 2027年10月 | 2029年3月 | ||
| 9番艦 | 2026年3月 | 2028年10月 | 2030年3月 |
尖閣列島など南西諸島に潜水艦を派遣するには、呉基地の方が距離的に近い。
したがって、たいげい型潜水艦も呉基地に多く配備される可能性がある。
尖閣列島やパシー海峡(台湾~フィリピンに位置し海峡幅100km・水深1500m以上)周辺に「そうりゅう型潜水艦」を含め常時5隻~8隻の潜水艦を配置しているとの情報もある。
まとめ
現行「そうりゅう型」でも中国軍に十分勝てるが、新型潜水艦「たいげい型」は、尖閣列島北側水域の浅海域(水深100m~200m)でも能力を発揮できるよう開発されている。
さらに、そうりゅう型から採用されている密閉型の永久磁石同期モーター(PMSM)搭載により、静粛性が高く、敵に発見されにくい。
また、次世代音響(ソナー)システムの採用により、敵探知を自動化し、敵潜水艦の探知能力が高まった。