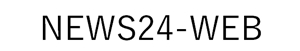2025年5月末から6月にかけて、中国海軍の空母「遼寧」と「山東」が日本周辺の太平洋に同時展開し、米空母打撃群との交戦を想定した迎撃演習を行っていたことが、複数の日本政府関係者の証言で明らかになりました。
この訓練は、中国海軍が「実戦的な空母対抗戦」を行った初のケースとみられ、台湾有事や南西諸島防衛を見据えた作戦能力の強化の一環と分析されています。
近年、中国人民解放軍海軍(PLAN)は空母戦力の増強を急ピッチで進めています。空母「遼寧」(001型)は2012年に就役、その改良型である「山東」(002型)は2019年に就役しました。
2022年に進水した最新鋭の「福建」(003型)は、世界でアメリカに次ぐ電磁カタパルト搭載空母で2025年に就役する予定です。
これら空母戦力の強化と並行して、中国は実戦を想定した訓練の質も大きく向上させています。特に注目されているのが「米空母との空母戦」を想定した迎撃訓練の実施です。これは単なる防衛演習ではなく、「米空母打撃群(CSG:Carrier Strike Group)」を現実の脅威と見なした実戦型訓練であり、東アジアの安全保障環境に重大な影響を与える動きです。
防衛省統合幕僚監部によれば、空母「遼寧」と「山東」は2025年5月下旬から6月中旬にかけ、沖縄本島、沖ノ鳥島、南鳥島の周辺海域に展開し、艦載機・ヘリコプターによる離着艦を合計で約1050回実施しました。これは過去最大級の規模です。
この期間中、特に注目されたのが2025年6月7日頃から約1週間にわたり行われた迎撃訓練です。
今回の演習では、2隻の空母が「敵味方」に分かれて行動しました。政府関係者の分析によると、「遼寧」が米空母の役割を担い、「山東」がそれを迎撃・追跡する側として動いた、という米空母との「空母戦」を想定したシナリオが採用されていたとみられています。
空母「遼寧」の動き
2025年6月7日ごろ、南鳥島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内を西に進み、第2列島線(小笠原~グアムライン)を越えて中国本土方向に進行。
空母「山東」の動き
同時期に沖縄本島の南方から東へ航行し、「遼寧」を迎撃する動きを演出。
このように、実戦に近い「空母戦」を想定した訓練が太平洋上で実施されたと考えられます。
興味深いのは、「遼寧」が「山東」に対して約500カイリ(約930km)の距離を取るような動きを見せた点です。これは、実際に米空母打撃群が他国艦艇と遭遇した際、偶発的衝突を避けるために一定の距離を保つ「航行規則」に近い行動とされています。
つまり中国海軍は、米空母の運用ルールや行動パターンを模倣し、訓練のリアリティを高めていたと分析されています。
このような動きは、単なる演習を超えて、「本番」に備えたシナリオシミュレーションであることを物語っています。
「迎撃訓練」とは、敵の攻撃を想定し、それを阻止・撃破する訓練です。ここで言う敵とは、主に米海軍の空母打撃群。つまり、「米空母が接近し、中国の沿岸部や軍事拠点を攻撃する」というシナリオを前提に、その動きを探知し、艦載機・ミサイルで反撃する能力を鍛えているのです。
中国の訓練では、以下のような要素が含まれています:
-
空母艦載機「殲-15(J-15)」による対艦攻撃訓練
-
艦艇・潜水艦・航空機による協同作戦
-
電子戦・通信妨害・情報戦の統合作戦
-
地上発射型ミサイル(DF-21D/26)との連携
これらの訓練は、単なる海軍単独の演習ではなく、「A2/AD(接近阻止・領域拒否)」戦略に基づいた、中国全体の軍事作戦能力を強化する目的を持っています。
1. J-15艦載機による対艦ミサイル発射訓練
中国の空母「山東」や「遼寧」から発進したJ-15は、長距離ミサイル(YJ-83など)を使用し、模擬標的艦に対する攻撃を実施しています。米空母への奇襲や先制攻撃を想定しており、複数機による一斉発射、電子妨害下での作戦など、複雑な環境下での訓練が行われています。
特に、2023年以降の演習では、空中給油や編隊飛行、夜間出撃などの高難度訓練も実施されており、作戦遂行能力の向上が見られます。
2. 電子戦・指揮通信訓練
米海軍は高度なネットワーク戦能力を持ちます。これに対抗するため、中国は電子妨害(ジャミング)、デコイ使用、指揮通信の分散化などを駆使する訓練を強化しています。特に人工衛星・ドローンを用いた情報収集との連携が進んでおり、米艦隊の探知・追跡能力も向上しています。
2024年には、空母艦隊と地上部隊間のリアルタイム情報共有訓練も報じられました。
3. 対潜戦訓練
米空母打撃群には原子力潜水艦(攻撃型原潜:SSN)が随伴しており、大きな脅威です。中国海軍は対潜水艦戦(ASW)に弱点を抱えていましたが、近年はZ-20型対潜ヘリや新型フリゲート艦を投入し、対潜探知・追尾・撃破の訓練を強化しています。
特に、南シナ海での対潜戦演習では、海中ソナー網と空中ヘリによる「複合探知ネットワーク」を構築しつつあります。
中国国防省は2025年6月末、空母「遼寧」と「山東」が「太平洋西部海域で互いを仮想敵として実戦的な対抗訓練を行った」と公表しました。この発表は、日本政府の分析とも一致しており、事実上、空母同士の対抗訓練を認めた形です。
演習期間中の2025年6月7日〜8日には、海上自衛隊のP-3C哨戒機が中国空母を監視していた際、中国艦載機から異常接近を受ける事案も発生しました。
これは、日本側が訓練情報を収集するのを妨害する意図であり、「圧力によって監視活動を断念させる」狙いがあったと見られています。航空法や国際慣習上も問題視される行動であり、偶発的な軍事衝突を引き起こすリスクも含んでいます。
今回の訓練は、中国の「A2AD(接近阻止・領域拒否)」戦略の実践と位置づけられます。
中国は、南西諸島~台湾~フィリピンに至る第1列島線の内側への米軍の侵入を阻止し、小笠原諸島~グアム~パラオを結ぶ第2列島線の外縁を守ることで、西太平洋全域での作戦自由度を高めようとしています。
今回、「遼寧」が第2列島線を越えて行動したこと、そして「山東」がその動きを封じる訓練を行ったことは、まさにこの戦略の一環であり、中国海軍の作戦ドクトリンが本格的に実戦化している証拠といえるでしょう。
2025年現在、中国はさらに強力な空母「福建(003型)」の実戦配備に向けて準備を進めており、電磁カタパルトによる艦載機の発艦能力や、新型ステルス艦載機「J-35」の導入も進んでいます。
この新体制が完成すれば、中国は空母3隻体制でのローテーション配備が可能となり、西太平洋でのプレゼンスは飛躍的に向上することが確実です。
自衛隊関係者の一人は、「今回の空母2隻の演習は、空母打撃群によるA2AD戦略の具現化を進めていることを示す明確なメッセージだ」と警戒を強めています。
中国空母による「米空母戦」想定の迎撃訓練は、単なる軍事演習ではなく、台湾有事や米中対立の火種となる可能性をはらんだ極めて現実的なシナリオの再現です。
一方で、訓練中の異常接近などは偶発的衝突のリスクを高めており、地域の安全保障にとって看過できない問題です。日米を含む関係国は、監視と抑止を強化すると同時に、緊急時の連絡体制や危機管理の再構築が急務となっています。
東アジアの海は、ますます「米中の空母対決」の時代へと突入しつつあります。
中国が迎撃訓練の仮想敵に「米空母打撃群」を据える理由は明確です。それは、米軍の軍事介入が最も現実的な脅威だからです。
たとえば台湾有事の場合、米国が空母を派遣して台湾を支援する可能性は極めて高く、実際に過去には第7艦隊が南シナ海や台湾海峡でプレゼンスを示しています。中国としては、これに対抗できる体制を構築する必要があるのです。
また、米海軍は「グローバル・ブルーウォーター・ネイビー(外洋展開型海軍)」であり、中国が太平洋進出を試みる際には必ず立ちはだかる存在でもあります。空母戦はその象徴的な戦場なのです。
中国の空母戦力は確実に進化していますが、現時点で米海軍と正面から対等に戦えるわけではありません。
-
艦載機(J-15)は旧型スホイを改修したもので、米F/A-18やF-35に劣る。
-
空母の稼働率や整備能力もまだ発展途上。
-
作戦統制(C4ISR)やドクトリンの面で差がある。
ただし、中国はこれを補う形で、地上基地・ミサイル戦力・ドローンなどの多層防衛を整備しています。特に「空母キラー」とも称される弾道ミサイルDF-21DやDF-26の存在は、米空母の接近を難しくする要因となっています。
中国の「空母対空母戦」迎撃訓練は、単なる防衛準備ではなく、地域覇権を視野に入れた戦略的シグナルでもあります。アメリカへの対抗心、台湾有事への備え、南シナ海の支配力強化――これらすべてが、訓練の裏にある政治的意図と読み取ることができます。
空母戦力とは単なる兵器ではなく、「移動する主権」「国力の象徴」ともいえる存在です。中国はその戦力を使って、東アジアの軍事バランスに挑戦しようとしています。
今後、空母「福建」の本格運用やJ-35の配備が進むことで、「アジアの空母時代」は新たな段階に突入することになるでしょう。その動向を注意深く見守る必要があります。